- 教科書の大事なところを抜粋して、掲載している
- 「Lesson 6 の内容(p.147から)
ページ数は、第6版と第7版で少しずれているかも、でも内容は同じ
- 教科書も目を通しておくこと
| 9.9 ***と### |
| 6.1 for文(教科書 p.148) |
| ・for文のしくみを知る - 構文(書き方)は Python と少し異なる for( 初期化の処理; 繰り返す条件; 更新処理 ){ 処理1; 処理2; : } 初期化の処理 ・・・ 繰り返しを開始するとき、はじめに実行される 繰り返す条件 ・・・ この条件が満たされる間、繰り返す 更新処理・・・繰り返しの1回ごとに行われる <基本的な使い方>
<ちょっと変わった使い方>
|
| 6.2 while文 |
| ・while文のしくみを知る - while文のしくみは基本的に Python と同じだが、書き方が少し異なる - また、 Python では while に else をつけることができるが、Javaでは else は使えない while( 繰り返す条件 ){ 処理1; 処理2; : } 繰り返す条件 ・・・ この条件が満たされる間、繰り返す <基本的な使い方>
<無限ループの例>
|
| 6.3 do〜while文 |
| ・
do〜while文のしくみを知る - while文はループの先頭で条件判断を行うが、do〜while文はループの末尾で条件判断を行う - while文との違いは、必ず1回はループの処理が実行されること - Python に do〜while文 はない(while文で代用できる) do{ 処理1; 処理2; : }while( 繰り返す条件 ); 繰り返す条件 ・・・ この条件が満たされる間、繰り返す |
| 6.4 文のネスト |
| ・for文をネストする - 繰り返しの文を入れ子(ネスト)にすることができる - for文を使ってネストする場合が多い <基本的な使い方>
実行すると以下のようになる 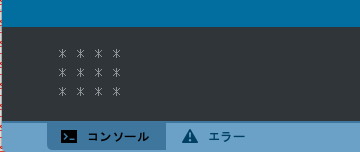 |
| 6.5 処理の流れの変更 |
| ・break文のしくみを知る - for文など繰り返しのループの中にbreak文があると、そこでループを抜ける <基本的な使い方>
・ switch文の中でbreak文を使う - switch文でbreak文の使い方を工夫すると、便利な処理ができる ・ continue文のしくみを知る - for文など繰り返しのループの中にcontinue文があると、そこからループの最後まで処理をスキップする for(int i=0;i<10;i++){ 処理1; if( x==i ) continue; // xとiが等しいとき、処理2、3、4はスキップされる 処理2; 処理3; 処理4; } |