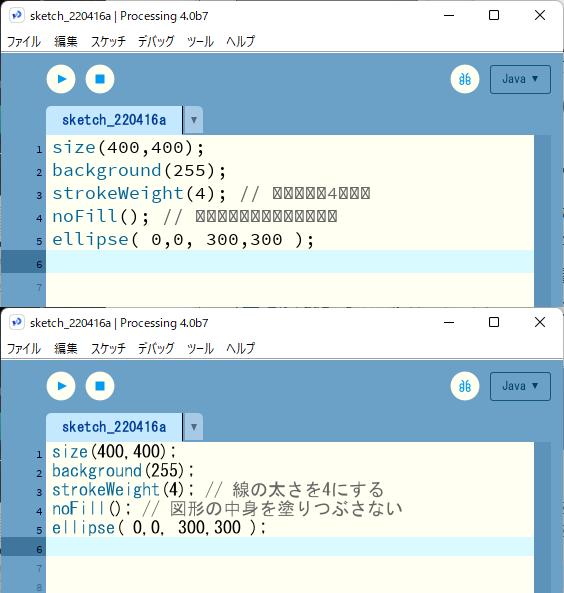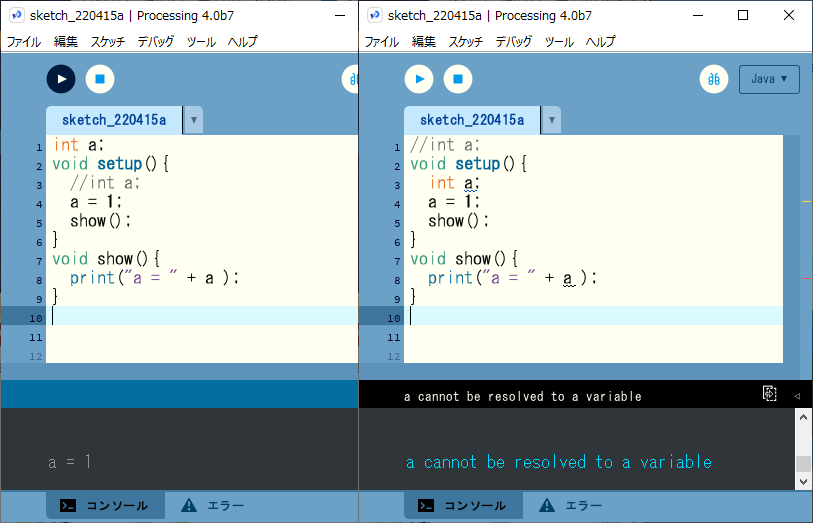- 変数の扱い、型、演算子、制御処理( if文 、for文 など)、クラス、・・・ はほぼ同じ
- Processingは Java に較べて
>グラフィックスや音声の利用が簡単
>アニメーションなど動きのあるプログラムを作りやすい
>マウス、キーボードの処理が簡単
などの特徴がある
- 実行方法はJavaと少し異なる
・ コンソールへの出力方法の違い
- Javaの場合
| System.out.println("good morning"); //<-- 改行あり System.out.print("Hello"); //<-- 改行なし |
- Processingの場合
Javaの System.out.println() および System.out.print() も使用可能だが、System.out を省略して
| println("good morning"); print("Hello"); |
<注意>
・ Processingのエディタで、日本語が文字化けする人は
[ファイル] --> [設定] を開き、下記の部分を変更してください。
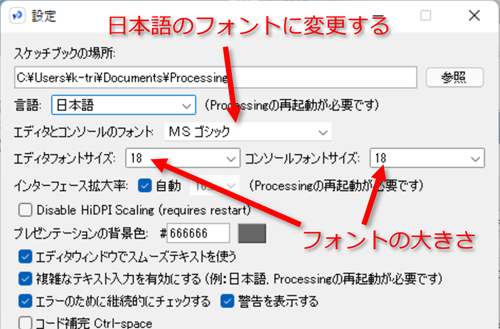
下の図で、上図は文字化け、下図は日本語が正しく表示されているものです